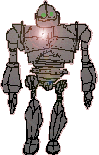
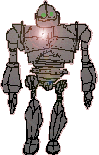
モナも自信をなくしていました。自分と言うものがつまらないものに思えてきたのです。
「私がこんなにたくさんいる。こんなにいるのだったら私一人いなくなってもどうということはないのじゃないかしら?私ががんばらなくても、誰かがマーを助けてくれるのではないかしら?」
万華鏡の中の不思議な光が、モナのがんばろうとする気持ちや自分を信じる気持ちをうばっていくようでした。
突然声がしました。それはマーの声でした。
「モナ、信じるんだ。自分を、そして仲間を。目を閉じて。そして君自身の心の声に耳をかたむけるんだ」
そしてモナ以外のみんなには
「彼女のために、彼女が大きな力を出せるように祈るんだ」というマーの声がはっきりと聞こえたのです。
モナは目を閉じました。数え切れないいくつもの自分の姿は消えました。そこにいるのは自分と、そしてスカートにつながっている大好きな仲間だけでした。
「私たちはどうすればいいのだろう。私たちはどこへいけばいいのだろう」
みんなはただモナの力を信じて祈りました。いつもはあわてんぼうで泣き虫でしっぱいばかりのモナだけれど、モナは魔女なのです。大事なときにはきっとがんばれるはず…
「がんばってモナ。信じるんだ、自分のことを」トーシーとダビッドソンとシューモとミウユウとそしてスナーコ博士の心からあたたかい光が広がってきて、モナの身体をつつみました。万華鏡のたくさんの光の中でも、目を閉じているモナにははっきりとその光が見えました。その光はやがて言葉では言い表せないような豊かなメロディとなって広がりました。そしてその光の中でモナははっきりとわかったのです。
「私たちのすすむべきところがわかった。それは海」
光と音楽はあふれるようにモナの身体をつつみ、モナの身体にやわらかく波が静かに入ってきたのです。
「to sea…海へ」モナがしっかりとした声でさけびました。そのときモナの手にしていた万華鏡の「トーシー」の字がまた光りました。そして気がついたときにはみんなは砂浜にいました。
「助かった…」ダビッドソンがうれしそうに声をあげました。けれど暑さが苦手なあなぐまのシューモは息をするのも苦しそうでした。そしてとうとう横になってしまいました。砂浜は森よりももっともっと暑く、そして乾いていました。
「ぐっと気温があがったようだ」スナーコ博士は心配そうにシューモを見ました。
「毛皮でおおわれているから、体温がどんどん上がっているのだろう」
「シューモさん、ごめんなさい。私のみつけた道であなたを危険な目にあわせてしまっているんだわ」でももうモナはあともどりをするわけには行きませんでした。
「さらに温度が上がったのは原因に近づいた証拠だよ」スナーコ博士はあたりをさっそく調べはじめました。
「シューモさん、待っていてね。私、心の声にしっかりと耳を傾けて進むことにします。いそいで戻ってくるから…待っていてね」
とても小さくて泣き虫で、そして弱虫のモナのどこにこんな力を秘めていたのでしょうか?、今はとても頼もしく、そして大きく見えました。シューモはこんなにつらくなっても、まだみんなと一緒にすすもうとしていました。よろけながら、立とうとするのです。
「僕たちにまかせておけよ。君はここに残ったほうがいい。それ以上進むと命さえ落としてしまうよ」ミウユウの言葉にシューモは
「ここにいても恐ろしく暑いし、つらいよ。でも一番つらいのは僕がみんなのために何ひとつできないことだよ。君たちは先にいってくれ。でも僕も僕の力で行くよ」
「おいていけないよ。そうだ、ちょっと待っていてくれないか?モナ10分だけだから」
シューモといつも仲良しのダビッドソンは、木で何かを作ることがとても上手でした。あっという間に浜辺にうちあげられた木でタイヤや軸を作り、やっぱり打ち上げられた板にとりつけて、台車のようなものを作りました。
「シューモ、ここに乗ってくれるかい?僕がひっぱっていくよ」
「力だったら僕だって、誰にも負けない」スナーコ博士は学者だったけれど、力もとても強いのです。
「ありがとう」シューモが涙をうかべました。
「よかった。ありがとう。ダビッドソンさん、ありがとう。スナーコ博士。ありがとう。シューモさん、では出発」浜辺はまるで砂丘のようにどこまでも続いているようでした。けれどそれは平らではなく、目の前には大きな大きな砂山が見えました。さらさらと崩れる砂山は、けれど、本当に大きく天までとどきそうなくらいでした。モナはその砂山へ向っていました。
(シューモをひっぱりながら、この足元の悪い、大きな砂山にいったいのぼることができるのだろうか?)誰もが心配になりました。
けれどモナは砂山にのぼることはせず、まわり込もうとしていました。モナの心がそうしろと教えてくれていたのです。
突然いちじくがウーと唸り声をあげました。砂山をまわりこむとそこには驚く景色が広がっていたのです。空中に大きな大きな宇宙船のようなものが浮かんでいたのです。そしてその宇宙船は白い水蒸気をシューシューとさかんに出していました。
その宇宙船はくすんだ黒い鉄の塊でした。あなぐまのシューモだけでなく、他のみんなもその暑さにもう何度も気を失いそうになっていました。
「モナ、何か近づいてきている」トーシーが低い声でモナに声をかけました。
いちじくもそれに気がついているのでしょう。モナを守るように何かに向って吠えつづけています。
ギーギーギーギー。一度聞いたら忘れることができない音がモナの耳にとどきました。銀色の光を持った金属のよろいを着たものたちが水蒸気のむこうから、少しづつ形をあらわしてきました。重い足をひきずるようにして歩く、前にモナが森のはずれで出会った銀色のものでした。
「おそろしく精巧にできているロボットだ」スナーコ博士がうめくように言いました。そのロボットは一体ではありませんでした。四方八方の水蒸気の霧の中から、何体ものロボットたちはギーギーと気味の悪い音をたてて現われ、そして近づいてきます。とうとうモナたちは銀色の身体に黄緑色に光る目をもつロボットたちに囲まれてしまいました。
シチュー6へ
シチューの目次へ
魔女の花びらへ