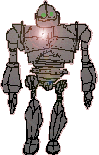
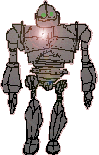
モナたちは銀色のロボットたちにとらえられました。みんながどんなに大声を出して叫んでも、たたいても、ロボットたちは知らんぷりで、心を持っていないのか、ただ誰かに命令されたとおりに仕事をこなしているように見えました。
ひとつのロボットが仲間をひとりずつ抱えました。抱きかかえられながらも「戦おう」というミウユウの言葉をモナがとめました。
「マーがきてほしいと思って、私たちを呼んでくれたのだと思うの。シューモさんも身体を動かせない…もう戦うのはよして、ロボットたちと行きましょう」
それまでロボットに歯をむきだし、ロボットの腕から一刻もはやく抜け出して、モナをロボットから救い出そうというふうに、ロボットに吠えていたいちじくが吠えるのをやめました。
「そうだ、おそらくロボットたちはこの暑さなど平気なのだ。僕たちはこの暑さの中では戦えないよ。無駄な争いはやめよう」スナーコ博士も冷静に言いました。
トーシーはもしかしたら同じ銀色だということで何か感じたのかもしれません。しきりにロボットに話しかけていましたが、ロボットからは何の返事も返ってはきませんでした。
ダビッドソンは親友のシューモを気遣い、ロボットの腕の中でもシューモから決して目を離さずにいました。
ロボットたちは水蒸気で前があまり見えない中を進んで行きました。
「マー」突然モナが声をあげました。モナの声にみんなマーの姿を探しました。マーは手足をひもでしばられた形で空中で浮かんでいました。そしてその前になんともおそろしげな巨大な生き物が顔を真っ赤にして、マーを大声で責めていました。
その生き物の灰色の肌には少しも毛が生えていませんでした。そのかわりにごつごつした毛穴からうみのようなものが流れ、一目でも見た人は決して忘れることができないくらい恐ろしい生き物でした。こんなにもみにくいものがいるだろうかと思われるくらいのすさまじさでした。怒っているからかときどきその毛穴からシューという音を出し、熱風があたりをまたいっそう暑くさせていました。「違う、前に食べたおまえのシチューの味はこんなじゃなかった。もっともっとおいしかった。シェフマー、おまえはもっとおいしい味を作れるはずだ」その生き物はいっそう赤い顔を赤くしました。シューと熱風が吹き、あたりの温度がまた一度上がりました。
「僕のできることはこれでおしまいだ。僕はいつも人の力を借りて、料理を完成しているのだ」マーが少し気の毒そうにその生き物を見ました
「それが不思議の森に住む魔女、モナの力だな」その声を聞いたからか、ロボットたちがギーギーと声を上げました。モナたちはそれがロボットの身体をすりあわせる音だと思っていたので、声を持っていることに驚きました。
トーシーが記憶をたどるように腕を組みました。「もしかしたら、あの生き物はユウラという名前の生き物かもしれない。昔マーが話してくれたことがあるよ。シチューを作ってシチューパーティの準備をしていたときに、ひょっこり戸口からその生き物はあらわれて、シチューを欲しいと言ったんだそうだ。一度見たら忘れられないくらい恐ろしくみにくい生き物だったとマーが話してくれたけれど、なるほど本当にそうだな。ユウラはシチューを口に入れたとたん怒鳴り出して、『シチューを全部くれ』と言ったのだそうだけれど、これからシチューパーティがあって、君はしっかり一人分は食べたからと断ると、すごい顔でにらみつけていなくなったそうだよ。どうも少し魔術を使うようだったとマーが話してくれたんだ」「そこでごちゃごちゃぬかしているのは誰だ。黙っていろ!!」ユウラがモナたちの方をふりかえりました。目は真っ赤にただれ、赤い顔はさらに赤くなり、耳まで裂けた口からは全身の毛穴から出している水蒸気よりももっとたくさんの熱い黄色い息をシューシューと出していました。
「モナ、おまえがモナだな。この俺様のシチューをもっとおいしくするんだ!俺さまの大事なシチュー。これを食べるために俺はとてつもない苦労をしたんだぞ」
ユウラが指差したのはモナたちが大きな宇宙船だと思った大きな黒い円盤でした。それは驚いたことに、とてつもなく大きな、おなべだったのです。中には森から運ばれてきたきのことしいの実などがたくさん入れられたシチューがたくさん、ぶくぶくと泡をたてて煮えたっていました。そのシチューを温めているのはどうやらユウラから出ている怒りのエネルギーのようでした。
「なんとすさまじいエネルギーなんだ」スナーコ博士はカバンからノートを取り出し、何かを計算しているようでした。モナは悲しそうに首を振りました。
「このままではもっとおいしくはならないの」
ユウラはウオーと悲しい声を上げました。その声はあたりじゅうに響き渡り、恐ろしい熱気があたりをつつみました。
「俺様はこのシチューを腹いっぱい食べたいためにどんなにどんなに大変な思いをしてきたと思うんだ。こんなにみにくく生まれついて、誰からも嫌われ、親しく話し掛けてもらうこともなく、みにくい、恐ろしい・・と化け物呼ばわりされてきた俺様が、もう死んでしまいたいと思って、時間の隙間からもうひとつの世界をみたときに、驚くほどおいしそうな匂いをかいだんだ。隙間からマーのなべの前に行き、あのシチューを食べたんだ。それはとてつもなくうまかった。もっともっと食べたかった。けれどマーはダメだと言った。俺様は死ぬ前にもう一度あのシチューを腹いっぱい食べてやると思って、たくさんのロボットを作り手下にした。計画をねって、それから一年眠ることすら忘れて準備し、秋がくるのを待っていたんだ。俺は俺をみにくいというものたちと別れをつげるために、命を絶とうと思っている。その前にどうしてもシチューを腹いっぱい食べたい…そのどこがいけないんだ。なぜ、マーは前と同じシチューを作ってくれないのか」
仲間たちは気の毒そうにユウラを見ました。けれど憎憎しげに吐く息を見るとその気持ちもたちまち消えてしまうのでした。モナはぐったりしているあなぐまのシューモの身体を抱きしめながら言いました。
「あなたは私の大事なシューモをこんなにもつらいめにあわせているわ。あなたがおなかいっぱいシチューを食べたいという気持ちは間違っていないけれど、でもだからと言ってあなたは人を苦しめていいということにはならないと思う」
モナはシューモをそっと横たわらせ、ユウラの前へ進みました。
「やけどをしてしまうよ、モナ。気をつけて」ダビッドソンが声を上げました。
けれどモナはユウラに手を差し出しました。
「ユウラさん私たち仲間になりましょう」
モナの手がユウラの手に触れたとき、モナの顔が熱さと痛さで一瞬ゆがみました。けれどモナはにっこり笑ってもう一度同じことを言いました。そして今度はしっかりと手をにぎりました。
「ユウラさん、私たちお友達になりましょう」その瞬間不思議なことがおこりました。ユウラの目から涙がぽろぽろとこぼれ、あたりに急に涼しい風が吹いてきたのです。
「俺をあなたと君は呼んでくれるのか?ユウラさんと呼んでくれるのか?そして仲間になろうと言ってくれるのか?俺は今まであなたなどと呼んでもらったことは一度もなかった。名前で呼んでもらったこともなかった。いつも『あいつ』とか『化け物』とか『きさま』とかそういうふうな呼ばれ方しかしたことがなかったんだ。その俺に、君は仲間になろうと言ってくれるのか?」
ユウラが声を上げてわあわあと泣くと、空から大粒の雨が降ってきました。いそいでロボットたちがなべに大きなふたをしました。あたりはすっかり冷え、秋の風がもどってきたようでした。
マーがその様子を見て言いました。
「僕の料理がおいしいのは、愛する人のおいしい顔を見たいと思うからだよ。大好きなモナは大好きな仲間たちにおいしい料理を食べてもらいたいと思って作るからだよ」
「マー、ユウラさんや私たちみんなで秋のシチューをいただくことにしたらどうかしら?マーが私たちみんなのために秋のシチューの仕上げをしたらきっとシチューはおいしくなるわ」モナがにっこり笑いました。
泣きながらユウラがロボットたちにマーの手足をしばっているひもをほどくように言いました。
雨もいつのまにかあがっていました。
時間の隙間ではいろいろなことができるようです。マーは雲に乗って、大きなシチューの味見をしました。
「ほんの一振りの塩と、コショウが足りないな。それからローリエの葉っぱが一枚」
本当にたったそれだけのことだったのでしょうか?それとも塩やコショウやローリエと一緒にマーや仲間のおいしくする不思議な調味料が入ったのでしょうか?シチューは完成しました。
「ユウラさん、私たちが仲間になったパーティと、それからね、秋はミウユウのお誕生日の季節でもあるんです。そのパーティを一緒にしたらどうかしら?ロボットさんたちも一緒に」
銀色のロボットたちの胸のあたりに光がぽっとつきました。仲間の一人に加えてもらえたことでロボットたちの心にまるで血が通いだしたかのようでした。ギーギーとうれしげなやさしげな声がそれを証明していました。
ユウラの顔はとてもとてもおだやかでした。そして喜びがあふれているようでした。赤い顔は白くなり、赤かった目はこうして見るととてもつぶらで可愛らしいのです。身体の毛穴のうみもすっかりかたまって、とてもおしゃれな水玉模様のようでした。
「ユウラ、君はなかなか素敵だよ。ほら顔をうつしてみろよ」ダビッドソンがロボットの身体に顔をうつすように進めました。
「俺は、鏡は…あの好きではないから…」ユウラはすっかり人が変わってしまって、とても恥ずかしそうに言いました。さっきまでの乱暴で恐ろしいユウラは姿を消してしまって、そこには恥ずかしがりやで、少し臆病なユウラがいました。
「大丈夫だから、とても素敵だよ」「ユウラさん、とっても素敵」みんながあんまりすすめるので、ユウラはおそるおそる目を開けました。
「これが俺かい?夢じゃないんだろうな」ユウラの目からはまた涙が流れました。
「今までの君だって、きっと本当はとても素敵だったんだよ。ただ人を恨んだり、怒ったりばかりしていたから、とても怖い顔だったんだよ」ミウユウの言葉にみんなうなづきました。
「パーティの用意ができたよ」マーはロボットたちとすっかり秋のシチューパーティの用意をすすめていました。
「シューモくん大丈夫?」ユウラがシューモを抱きかかえると、不思議にシューモはすっかり元気になりました。
「君には人を元気にする不思議な力があるんじゃないかな?」トーシーが言っても、「まさか」と言ってユウラはなかなかそのことをうけとめようとはしませんでした。
「でもね、ユウラ。つらい思いをしてきた人はそのつらさの分だけ、悲しい思いをしてきた人はその悲しみの分だけやさしくなれるんだよ。君はこれまでとてもつらく悲しい気持ちですごしてきた。だからきっと君はとてもやさしくなれるに違いないよ。いや、もう誰よりも優しい人になってるよ」
「この俺が?この俺がとてもやさしい…?まさか。嫌われ者で、汚れもので、乱暴者のこの俺が?」「さあさあ、シチューがさめてしまうから」マーの声で仲間たちはテーブルにつきました。テーブルにはたくさんの食べきれないシチューと、それからトーシーとモナとスナーコ博士が持っていた3個のなしで作られたジュースが置かれてありました。
「秋のシチューパーティばんざい。ユウラが仲間になっておめでとう。ミウユウお誕生日おめでとう」
「乾杯」乾杯のジュースは素晴らしくおいしく、暑さで乾いたのどをうるわせてくれました。
「君から最初に食べてくれないか?」マーがユウラに言いました。みんなもユウラの口元と表情を見つめていました。
ゆっくりとスプーンでシチューをすくって,ユウラはシチューを口の中へ運びました。
「う…ウオー。これだよ。この味だよ。何度も夢にみたこの味。いや、まてよ。違う、前に食べたときよりももっともっとおいしいよ」
「きっとそれはみんなで食べるからだと思う。私も一人で食事するときより、大好きな仲間と食事をするとおいしいから…あのね、これも食事の仕上げの魔法のひとつだよね、マー?」
「そうさ、みんなで食べる食事はおいしい」本当においしいおいしいシチューでした。
すっかり元気になったあなぐまのシューモがユウラに言いました。
「僕のうちのとなりの木が空いているんだ。そこに君、住まない?僕の家とおんなじで、そこはそんなにりっぱな家じゃないけど、でもなかなかすごしやすいよ」
ユウラも森にすむことになりました。
「秋のシチューパーティが終わったら、みんなで手をつないで、また万華鏡をのぞけばおそらく森へ帰れると思う。しかし時間の隙間は我々の森の世界と同時に存在しているわけで…それからいったい、空間と時間と……」スナーコ博士がまた計算を始めました。
森に帰るころ、森にも秋の風が吹いていて、葉っぱもすっかり秋の色にそまっていることでしょう。おしまい
シチューの目次へ
魔女の花びらへ