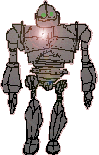
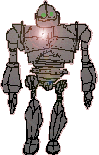
秋になるとシチューがたべたくなるなあとミウユウは思いました。そして今シチューを食べたくなったから、きっと秋になったのに違いないとミウユウは思ったのです。ミウユウがそう思ったのには理由がありました。秋になるとミウユウの誕生日がやってきます。ミウユウには好きな食べ物がたくさんあるけれど、とりわけシチューが大好きです。だからミウユウの誕生日のごちそうはいつも、何日も煮こんだシチューと決まっていたのです。
それにしてもこのところとても、暑いのです。もうお日様はずいぶん早い時間に山に沈んでいくのです。だからとうに秋になっていてもいいはずなのに、この暑さはいったいどういうことでしょう。
ミウユウは不思議に思っていることがありました。「シチューが食べたくなったのに、山にはきのこが生えていない…この暑さのせいだろうか」
ぶつぶつぶつぶつ言いながら、山道を歩いていました。
向こうのほうからやってきたのは、アナグマのシューモでしトーシーューモはきのこのある場所を誰よりもよく知っているのです。
あなぐまのシューモもやっぱり何かぶつぶつ言いながら下を向いて、何かを探しているようです。
「やあ、シューモ。どうだね、今年のきのこの具合は、僕は少しもみつけられないんだがね。シューモはきのこが生えている場所をちゃんと知っているんだろう?」
「それがおかしいんだ。確かにきのこがはえていたあとはあるんだけれど、みんな誰かに先回りしてもう取られてしまってるみたいなんだ。僕より先に、きのこを見つけられるなんて、いったい誰だろう。森に住んでいるものたちの顔を思い出してもちっともわからないよ。ミウユウは心当たりがない?」
けれどミウユウにももちろん心当たりなどあるはずがないのでした。
「ねえ、シューモ、それにしてもこんなに暑いのはどうしてなのかな?」
「朝から『暑いね』の挨拶は17回目だよ。もう暑いねというあいさつはたくさんだよね」……シューモはまた何やらぶつぶついいながら、汗をふきふきまたあたりを探し始めました。。
ミウユウはどこからかいい匂いがしているようなのに、気がつきました。
「誰かがシチューを作っているのかな?」
シチューのことばかり考えていると、なんだかどこからともなくシチューのにおいがしているような気さえしてきました。
「ああ。ますます食べたくなってしまうよ。きのこがダメなら、くりやしいのみを探せばいいんだ。木の実のシチューもなかなかいけるんだよね」ミウユウはつばをごくんと飲み込みました。
「うん、そうだね、きのこもいいけど、木の実もいいものね」シューモもミウユウの意見に賛成して、さっそくふたりで木の実を探すことにしたのでした。
けれど、どうしたことでしょう。いつもだったら森じゅう、どこにでも木の実が落ちていていいはずなのに、今年はどういうわけか、木の実もほとんど落ちていないのでした。「木の実といえば、ダビッドソン。ダビッドソンなら知っているはず…木の実のありか…」ミウユウとシューモは歌うように森の北側に住んでいるダビッドソンの家にいそぎました。
ダビッドソンの家は大きな大きなしいの木のほこらの中にありました。ダビッドソンがしいの木の周りを手を後ろに組みながら歩いているのが見えました。彼もなにやらひとりでぶつぶつ言っているようでした。
「おかしいぞ、おかしいぞ、木になっているのは、まだ少し青いしいの実ばかり、明日とろうと思っていた、食べ時のしいの実が、ああ、すっかりなくなっている…」
「やあダビッドソン、暑いね」ミウユウがダビッドソンに声をかけました。
「本当に暑すぎるよ。だけど僕は今、それどころじゃないんだ。冬じゅう食べようと思っていトーシーいの実クッキーが作れないよ。とり時のしいの実がなくなってるんだ」
「え?しいの実も?きのこもないんだ。この暑さと僕は何か関係があるような気がしてならないんだ」
「昨日はしいの実はしっかり枝になっていたんだ。でも足跡も、においも残さず、しいの実がなくなってる。そして今日もとても暑い…。暑いのとしいの実がすっかりなくなったのが関係あるかどうかわからないけれど、でも、しいの実がなくなったのは不思議で、こんなに暑いのも不思議。不思議という意味ではおんなじだな」ダビッドソンは腕を組んで考え込みました。ミウユウは手をぽんとたたいていいました。「どうだろう。スナーコ博士のところに行ってみようよ。博士ならどうしてこんなに暑いのか?きのこやしいの実がどこに消えたのか教えてくれるかもしれないよ」
「うん、それはいい考えだ。なにしろスナーコ博士はいつもとてもむつかしいことを考えているからね。しいの実のありかを知っているかもしれないよね」「きのこのありかもね」
スナーコ博士の家は、森のはずれにありました。空には大きな展望台がついていて、家の中には顕微鏡や虫眼鏡、それから何をするのに使うのかわからない大きな機械がたくさんありました。
ミウユウとシューモとダビッドソンが家に近づくと、ドアのところに銀色ぎつねのトーシーが大きな梨をかかえて中をのぞいていました。
「どうしたの?」ミウユウがたずねました。
「モナに梨を持っていったら、『スナーコ博士にひとつ持っていってもいい?さっき寄ったら、研究に夢中みたいだったから、きっと食べることも忘れてる』ってモナが言うんだ。だから帰り道だから僕が持っていくよって言って、ここにきたんだけど、声をかけてもスナーコ博士は計算に夢中で気がつかないみたいなんだ。」
モナは森にたった一人の魔女でした。でも魔女といってもまだまだ子供の修行中の魔女でした。森の魔女になってまだ間もないので、使える魔法もほとんどないのです。「いったい何を計算しているんだろう」
中をのぞくと、スナーコ博士は机にむかって、すごいスピードで何か書いたり、電卓をたたいたりしていました。
「みんなで呼んだら聞こえるかもしれない」ミウユウは「イーチ・ニー・サーン」と号令をかけました。
「こーんーにーちーはー」4人で大声であいさつをするとスナーコ博士はびっくりして椅子から転げ落ちてしまいました。
「なんだね突然に大きな声で。ああ驚いたなあ。みんなそろっていったいどうしたの?」
「うんと前から声をかけていたのだけど、ちっとも気がつかないのだもの。はい、とれたての梨だよ」銀色きつねのトーシーはスナーコ博士にずっしりと重い梨を渡しました。
スナーコ博士が梨のお礼を言っているあいだももどかしくて、シューモが聞きました。「ね、何を計算してたの?もしかしたら、どうしてきのこがないかとか…」
「どうしてしいの実がないかとか」
「それから、どうして暑いのかとか、ね。計算して考えていたの?」
スナーコ博士はうーんと腕組みをしました。
「ああ、きのこがなくなってるって?しいの実もなくなっているって?暑いだけじゃないんだな。大変だ。植物にも影響が出始めたのかな?うーん。謎だ。地球の軌道は少しもかわっていないんだ。太陽に近づいているわけでもない…しかし、気温は確実に上がっている。一日に一度ずつ。このままだと大変なことになる」
「きのこシチューはどうなってしまうんですか?」ミウユウが心配そうに聞きました。
「しいの実クッキーはどうなってしまうんだろう?」ダビッドソンも心配でたまらないのでした。
「きのこやしいの実どころじゃなくて、この森はもっともっと暑くなって、みんな黒焦げになってしまうかもしれない…この計算だと、あと一月もしないうちに、動物も草も木もみんな死んでしまうよ」
トーシーが大きな銀色のしっぽできびすを返すようにしながら言いました。「僕はモナのところへ帰るよ。モナは魔女だもの。計算でわからないことなら、今度はモナに聞いてみないといけないよ」
まだ修行中のモナに、スナーコ博士でもわからないようなむつかしいことがわかるとはミウユウもシューモもそしてダビッドソンも思わなかったけれど、でも大変なことがおこるのなら、モナのところに急ごうとみんなは思ったのです。なぜって、理由はこうでした。
「大変なことが起きるならあの子のとこにいかなくちゃな。なぜってあの子ときたら…」
「大変なおっちょこちょい」ミウユウが声をひそめて言いました。
「それからすぐに迷子になる…」ダビッドソンがうなづきながら言いました。
「それからとても泣き虫」シューモもうなづいて言いました。
「いつも失敗ばかり…」
「助けにいかなきゃしょうがないよね」
「そういう計算になるな」スナーコ博士も賛成しました。モナにはきまった家がありませんでした。ただ森の一番奥深くの大きなぶなの木が集まっているところにモナはいちじくという変わった名前の犬とたいていいました。覆いしげったぶなの葉がモナといちじくの身体を雨や風や寒さや暑さから守ってくれました。モナは温かなやわらかなこけのじゅうたんの上に、こけを傷つけないようにふうわり座ったり眠ったりするこつを覚えていました。
ミウユウとシューモとダビッドソンとスナーコ博士と、そして銀ぎつねのトーシーがやってきたときに、モナはいつもの緑色の服を脱いで、それを木の枝と枝の間にわトーシーたロープに干していました。
5人がいるのに気がついたモナはいいわけするように言いました。
「ちょっと川にすべって落っこちちゃったの。ほら、暑いから…ついでだから少し泳ごうと思って泳いだの。洋服も洗えてちょうどよかったの」
「川におっこちちゃう魔女もめずらしいよね」とミウユウが言いました。その言い方はダメな魔女だなあと言うのではなくて、だから心配なんだよねというあたたかい言い方でした。
けれどモナはミウユウの言葉に返事をすることを忘れて言いました。
「川って冷たいものだよね。今日の川はあたたかだった」
「それにね、なんだか変だった。鮭たちがおびえていたの。ずいぶん数も減っていたの」
「モナ、森がどんどん暑くなっている…」
「それからきのこがなくなってるんだ」
「それからしいの実もなくなってるんだ」
「大変なことになってるんだ。モナ…食べ物もなくなって、僕たちはみんな今に黒焦げ」
みんなは大きなぶなの木の近くの切り株や倒れ木にすわって、腕を組んで考え込みました。「でもトーシーはとてもおいしい梨を持ってきてくれたわ。梨はなくなっていなかったのね」
「梨は普段とかわらなくあったよ。リンゴも大丈夫だ」
「梨もリンゴもシチューには入れられないからね」ミウユウがぽつりとつぶやくように言いました。
そのとき、ダビッドソンはふと気がついたことがあったのです。「モナ?マーにはいつ会った?」
マーはこの森に、これもたった一軒のレストランのシェフさんでした。マーは世界中いろいろなところへピカピカにみがきあげた自慢のバイクででかけていきます。そしてそこで一度でも食べたことのある料理なら、まったく同じように作り上げることができるのです。
マーはモナのところへ「ちょっと味見してくれない?」ということを理由にして、いつもお料理を持ってきてくれるのでした。モナがおいしそうに食事をするのをとてもうれしそうに見ながら、マーはいろいろなお話をしました。今日お店に来てくれた人のこと、星のこと、空のこと、そして世界中旅してみつけたおもしろいものの話。
マーはモナに話をするのが好きでした。今まで気がつかなかったことが、話をしているうちに自分の中に大切なものとなって輝き出すのはよくわかりました。モナがもっともっとゆっくり食べてくれるといいのになとマーはよく思いました。(だって味見をしてもらってるんだから、それ以上のモナの時間をとるのはよくないよ)と思っていたのです。でも実際モナにはありあまるほどの時間があったのです。みんなも、それからモナ自身も気がついていないけれど、モナの周りではそこだけゆっくり時間が流れていたのでした。
「おいしかったかい?」
「ええ、とても。ありがとう」
「いやこちらこそ。モナに味見をしてもらわなければ、料理は完成とは言えないからね」
そうしてマーはまたレストランに帰っていくのでした。「ええ、そうなの。マーがこのところずっとここへやってきていないの」
モナに続いて、ときどき一緒に味見をするトーシーも言いました。
「本当に不思議なんだ。遠くへバイクででかけるときはいつだって、『明日から,モンゴルだよ。それでお願があるんだけれど、旅に出るので、余った料理のしまつに困っているんだ。腐らせちゃうからね』っていう具合に言って、とてもおいしいお料理を持ってきてくれるのに、そういう挨拶もないまま、姿を見せないんだものね」
「やっぱり変だよ」ダビッドソンはとても大変なことに気がついたように息をきらすようにして言いました。
「秋になると、いつもマーはきのことしいの実と鮭の入った秋のシチューを作るんだ。だから僕のところに、『とびきりおいしいしいの実を少しわけてくれないか』って必ずやってくるのに、今年は来ない」
「本当だ。きのこを分けてほしいって言いにこないよ」シューモも言いました。
「きのこに、しいの実に、鮭。そしてシェフマーの失踪…。うーん、計算できそうだな」スナーコ博士の思いにみんなうなづきました。
いちじくがクーンとせつなそうに鳴きました。
見るといちじくはモナの様子が変なのを感じていたのです。「どうしたの?何か思い出したんだね。何か気がついたんだね」トーシーはモナのそばにきて、下からモナの顔をみつめて言いました。
「私、本当はこのごろずうっと怖かったの。何日も前の夜、それからゆうべもそう。私不思議なものを見たわ」
「どこで…」ミウユウはできるだけモナを問い詰めるふうにならないようにそおっと聞きました。
「ぶなの木の森をぬけて、空が見える丘で…」
「それはいつ?」シューモもやっぱり静かにやさしく尋ねました。聞きたい気持ちで心はいっぱいだったけれど、モナがつらくないように、やっぱりシューモも見守るようにモナを見つめていました。
「あのね、昨日と今日の間の時間。0時でもない、あいだの時間」
「われわれが入りこめない時間の割れ目のことだね」スナーコ博士が電卓をそっとたたいてうなづきました。
「何を見たの?」ダビッドソンがそっと尋ねたとき、みんなごくりとつばを飲み込みました。
モナは遠いところを見るようにして、まるで物語を話し始めるように、静かに話しだしました。
「なんだか落ち着かなかったの。ブナの森はかわらずやさしくつつんでくれていて、こけも変わらずやわらかだったのに、私、なんだか落ち着かなかったの。急に不安になって、さびしくなって、いちじくにお散歩に行こうかとさそったの。ブナの森を出て、空が広がったとたん、とても驚いた。ゆうべはキラキラした細かいものが静かに空へ上がっていったの。たぶんそれはしいの実が月明かりに光っていたのだと思うの。それから傘をひろげたきのこもまるで踊ってでもいるように空へあがっていったの。数え切れないくらいのきのことしいの実だった…川の方でもきのこよりもしいの実よりもずっと大きな影が上がっていったの。私怖くなって、それで逃げてしまったの。今日はいったいその大きな影が何だったのか気になって、川へ見にいったの。中をのぞいていたら、鮭が私にお話をしたがっているみたいと思ったの。それで中をのぞきこんでいたら、落っこっちゃったの。何日か前の夜には、川から水が音もなく上がっていくのが見えたの。それから向こうの方で、やっぱりとても大きな影が上がっていった。もしかしたら、もしかしたら…。それなのに、私、ただぼおっと見ていただけだった…何にもしないで…」
モナはそこまで言うと、お話をやめてしまいました。モナのほおには涙がたくさん流れていました。
「モナ、もうお話は少し休みにしよう。ちょっと横になったほうがいいよ。そのあいだに僕たちは少し相談をしよう」ミウユウの意見にみんなうなづきました。2へ
シチューの目次へ
魔女の花びらへ